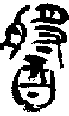| 邑 |
 |
住居のかこい囗とひざまづいた形からなる。人のいる場所、ひいてむら、国。部首の 、おおざととしては村落、地名、国名氏族名に用いる。 、おおざととしては村落、地名、国名氏族名に用いる。 |
|
| 邦 |
 |
部族の集まっているところの意
 (邑)と、音を表し同時に方域を示す (邑)と、音を表し同時に方域を示す ボウ(境界を示す繁茂した樹木)からなる。方域内の部族、ひいてくにの意 ボウ(境界を示す繁茂した樹木)からなる。方域内の部族、ひいてくにの意 |
|
| 邪 |
 |
むらを意味する と、音を表す牙ガとから成る。もと斉の琅邪(ロウヤ)郡の地名。よこしまの意に用いるのは と、音を表す牙ガとから成る。もと斉の琅邪(ロウヤ)郡の地名。よこしまの意に用いるのは ジャの借用。当用漢字は俗事。 ジャの借用。当用漢字は俗事。 が旧字 が旧字 |
|
| 郁 |
 |
 (邑)と、音を表す有(ユウ、イクは変わった音)からなる。もと地名、さかんなさま (邑)と、音を表す有(ユウ、イクは変わった音)からなる。もと地名、さかんなさま
意に使うのは イクの借用 イクの借用 |
|
| 郊 |
 |
 (邑)と、音を表し同時にひろい意(広コウ)を示す交からなる。むらはずれの広々とした所 (邑)と、音を表し同時にひろい意(広コウ)を示す交からなる。むらはずれの広々とした所 |
|
| 郎 |
 |
村を表す (邑)と、音を表す良リョウ、ロウとからなる。もと魯の地名。おとこの意に用いるのは良ロウの借用 (邑)と、音を表す良リョウ、ロウとからなる。もと魯の地名。おとこの意に用いるのは良ロウの借用 |
|
| 郡 |
 |
村を表す (邑)と、音を表し同時に集まる意(群)を示す君 (邑)と、音を表し同時に集まる意(群)を示す君
クンからなる。村落の集合体 |
|
| 郭 |
 |
人の集まるところの意の 邑)と音を表し同時にめぐらした城壁 邑)と音を表し同時にめぐらした城壁 を示す享キョウ(カクは変わった音)からなる。住民を守る囲い。 を示す享キョウ(カクは変わった音)からなる。住民を守る囲い。 |
|
| 郷 |
 |
旧字体の郷は食器に食物をもり、二人の人が向かい合って食べている。音は向かい合う(向コウ・キョウ)からくる。昔は部落の人が集まって宴会をしたので、そのような部落を郷いった。 |
食卓に迎えて歓迎するということが敵意のないことの証明、ひいては国境や城壁が無用となるように、世界平和は食糧問題解決から、、、というのは少し無理なこじつけか?豊かな飽食(グルメ)の時代にあっておじさんは未だ飢餓の記憶がぬぐえないでいるのでェ〜す。でも、ほんとに日本の農業(食料)政策大丈夫かなぁ?宝石みたいなトマトはいらない! |
| 郵 |
 |
村を表す (邑)と、辺境を意味する垂スイからなる。辺境の村。昔はそういう所が宿場につかわれたので宿場の駅の意。そこに旗( (邑)と、辺境を意味する垂スイからなる。辺境の村。昔はそういう所が宿場につかわれたので宿場の駅の意。そこに旗( ユウ)をたてたのでユウの音となる。 ユウ)をたてたのでユウの音となる。 |
|
| 酉 |
 |
酒をかもす酒壷の形 |
|
| 酋 |
 |
酒壷の上に、よい香りがたつさまを示す八とからなる。香気がたつよく熟した酒の意 |
|
| 酔 |
 |
酒と、音を表し同時につくす意(畢ヒツ)を示す卒ソツ(スイは変わった音)からなる。酒を十分に飲み尽くして酔う意。 |
こういうと酔っ払いが少し立派に見えてくる?こないこない! |
酬
|
 |
酒と、音を表す州からなる。主人が客に酒をすすめる。客の好意にこたえる意。ひいてむくいる |
応酬ということは、互いに相手をやりこめるということではなく、酒を勧め合うことが語源でしたか?もっとも「一気のみ」かいって好意だか悪意だか正体のわからない歓迎もありますね。 |
| 酸 |
 |
酒と、音を表し同時にさす意(鑽サン)を示す(サは変わった音)舌をさすようなすっぱい酒。 |
|
| 醒 |
 |
酒と、音を表し同時にはっきりする意(清セイ)を示す星セイからなる。酒の酔いがさめる。 |
|
| 醍 |
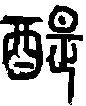 |
酒と、音を表す是シ(テイは変わった音)とからなる酒の一種。醍醐はまじりけのないバター(牛酪)の類。仏教語では仏性、仏法の妙趣。 |
??経験した人しかわからないでしょうね。言葉では説明できないのだとおもいますよ、、 |
| 醜 |
 |
 酉(さけ)と髪にかざりをつけた巫女が神前にさけをそそぐ形を表す( 酉(さけ)と髪にかざりをつけた巫女が神前にさけをそそぐ形を表す( のち鬼と書かれる)とからなる。神に仕える人。後世神に仕える人を忌(イ)むようになったので、きらう意。ひいてみにくいとなった。 のち鬼と書かれる)とからなる。神に仕える人。後世神に仕える人を忌(イ)むようになったので、きらう意。ひいてみにくいとなった。 |
前出の鬼を参照すると興味深い。エクソシストも神がかりの女性も現代の話です。偏見をもってはいけないけど、妙に説得力がありませんか? |
| 醤 |
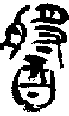 |
酉(さけ)と、音を表す将からなる。酒に塩や肉を入れて作ったしおから。 |
食の知恵はとっても古くから発明されているのはおどろきです。というよりも味覚ってあまり進化しないのじゃありません? |


 が旧字
が旧字
 イクの借用
イクの借用





 ユウ)をたてたのでユウの音となる。
ユウ)をたてたのでユウの音となる。





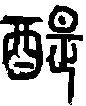

 酉(さけ)と髪にかざりをつけた巫女が神前にさけをそそぐ形を表す(
酉(さけ)と髪にかざりをつけた巫女が神前にさけをそそぐ形を表す( のち鬼と書かれる)とからなる。神に仕える人。後世神に仕える人を忌(イ)むようになったので、きらう意。ひいてみにくいとなった。
のち鬼と書かれる)とからなる。神に仕える人。後世神に仕える人を忌(イ)むようになったので、きらう意。ひいてみにくいとなった。